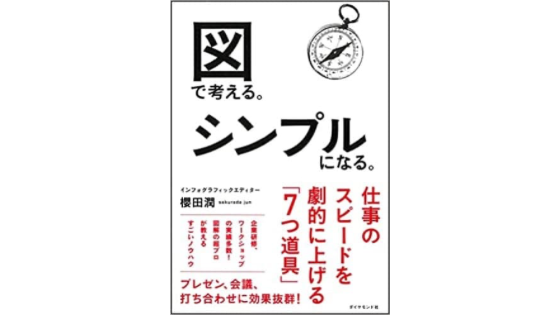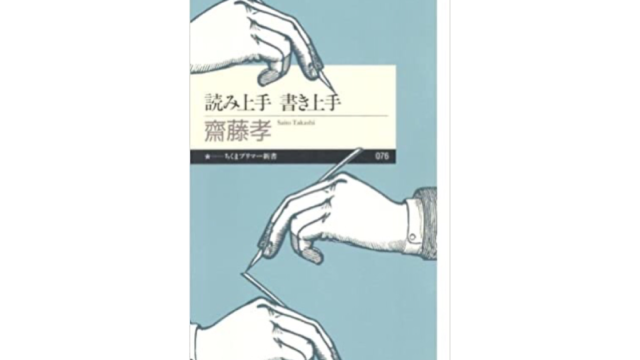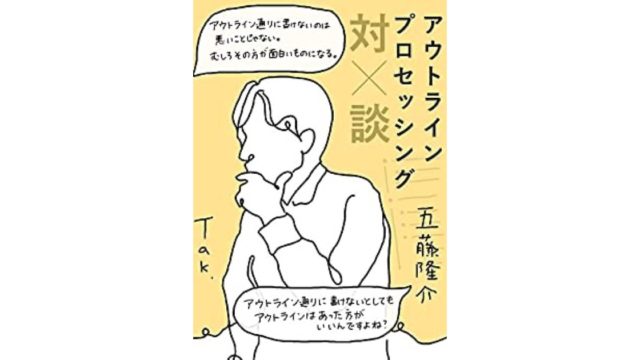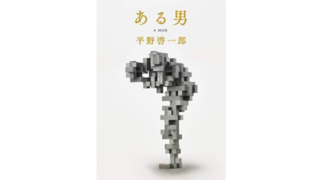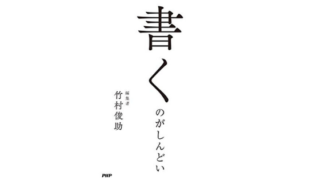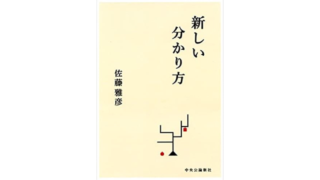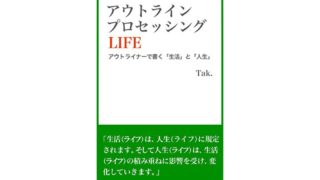「読書の目的は "楽しむもの" であり、自己の成長は二の次」が モットーの 小田やかたです。
本ブログは、読後、すぐに頭に浮かんだ偽りない感想を素直に綴っています。1分で読める分量なので、気軽に読んでいただき、ぜひ、選書の参考にしてください。今回読んだ本はこちら。
図解に関する基本的な知識が詰まった本です。
シンプルでわかりやすい内容で、図解初心者の教科書としては、本書を徹底的に読み込めば、これ1冊で十分ではないかと思いました。
冒頭に出てくる「桃太郎」を図解する例題。
やみくもに図にすればいいってものではない、ということがわかります。
同じテーマであっても、完成した図を見比べると、「その人が何を考えたのか」がにじみ出てきます。
どこにポイントを置くか、「視点」が大事であり、図解を見れば、その人がどういう視点で思考したかがわかるということです。
また、図解は「理解の型」が生まれるというのは眼から鱗でした。
図解すると思考が深まることがありますが、まさに理解の型にはまるからでしょう。
図は、形が決まったパーツの組み合わせなので、表現が限られます。その結果、「こういう内容を理解したいときは、この図を使って考える」といった具合に“理解の型” が生まれます。 ①思考プロセスそのものが単純化する ②シンプルなパーツの組み合わせだから、無駄がない
そいういう意味で、図解はプレゼンだけのものではありません。
齋藤孝氏も以下の著書で述べていますが、思考を助けるために図解する(同著書では「図化」と言っています)という用途も大事です。
これは本書で著者が勧めるトレーニングにも通ずるものがあります。日頃から何かを考えるときは図にしながら取り組むと思考が深まるし、図解のトレーニングにもなって一石二鳥かもしれません。
こうした寓話や、日常生活で目にする光景などは、「図で考える」最高のトレーニング題材 です。「資料作成のときだけ図で考える」。これではいつまでたっても身につきません。