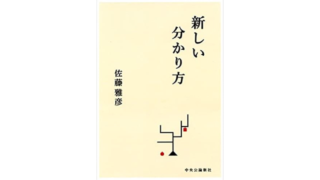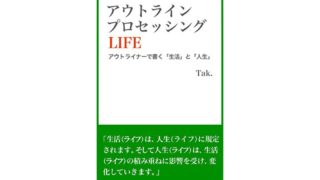「読書の目的は "楽しむもの" であり、自己の成長は二の次」が モットーの 小田やかたです。
本ブログは、読後、すぐに頭に浮かんだ偽りない感想を素直に綴っています。1分で読める分量なので、気軽に読んでいただき、ぜひ、選書の参考にしてください。今回読んだ本はこちら。
このたび KDP(Amazon Kindle ダイレクト・パブリッシング)で『これで読書ノートが続く!本を探す・読む・活かすを効率的にする Kindle×Evernote 読書術』を出版しました。
読後の「読みっぱなし感」というか、本を読んだのに「何も残っていない感覚」を味わうことはありませんか。
楽しかった、面白かった、という感想だけで終わるのも悪くはありませんが、それだけではなく、読書から得たものを明確にし、自分にとって役立つ読書にしたい。
そのために本書では「読書ノート」を作ることを提案します。
本書では、10年以上、試行錯誤をしながら読書ノートを作り続けている私の手間なく効率的で役立つ読書ノート作りのノウハウをお伝えするとともに、新刊やセールの情報収集、蔵書管理、読後の活用など、読書にまつわる工程を効率的に行うノウハウも紹介します。
本書の構成は次のとおりです。
第1章「探す」
1.新刊を効率的にチェックする
(1)ほしいものリスト内のセールをチェックする
(2)セール情報を網羅的にチェックする
(3)他のAmazonのセールもチェックする
2.セール本を効率的にチェックする
3.KindleUnlimitedのみを対象に検索する
4.蔵書管理サービスを使う
(1)読書状況も分析できる「ブクログ」
(2)「ブクログ」への効率的な登録方法
5.Kindle本の整理は「ジャンル」×「テーマ」
6.未読と既読の管理
◎Column① 電子書籍か、紙の本か
第2章「読む」
1.電子書籍は何で読むか
2.4つの効率的な読み方
3.主観を重視した「主観三色方式読書」
4.手書きノートアプリを活用した「図解メモ読書」
5.Kindleアプリの機能を使いこなす
6.「耳読」のススメ
◎Column② オーディオブックは「Audible」か、「 audiobook. jp」か
第3章「作る」
1.読書ノートは面倒なのか
2.読書ノートを作る意義
(1)読書を自分に活かす一番の近道になる
(2)自分だけの知識や知見の倉庫になる
(3)本から得た知識や知見を簡単に検索できる
(4)Kindle本が読めなくなっても大事な部分は読み返せる
(5)読後の思考が深まる
3.読書ノートに何を書くか
【レベル1】 ハイライトの引用
【レベル2】 ハイライトの引用+レビュー
【レベル3】 ハイライトの引用+レビュー+自分の設定項目
4.読書ノートの具体的な作成手順
(1)Kindle本の場合
(2)紙の本の場合
(3)オーディオブックの場合
5.「Evernote」のススメ
◎Column③ 私の読書ノート
◎Column④ 多様な読書ノートの作り方
第4章「活かす」
1.レビューを発信する
2.読書ノートを見返す仕組みを作る
3.読書ノートを活かすポイントは検索と項目別の見返し
4.読書ノートは作って終わりではなく育てるもの
5.モバイル書斎化構想
◎Column⑤ ブクログで読書傾向を知る
目次をご覧になって少しでも興味のある内容がありましたら、ぜひ、手に取ってみてください。